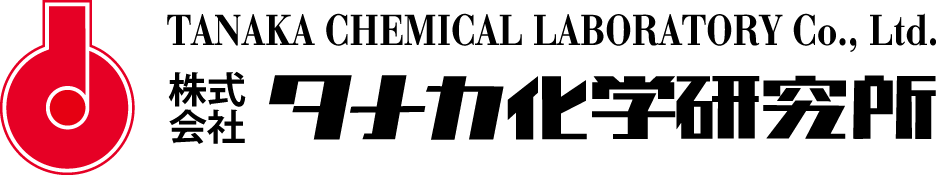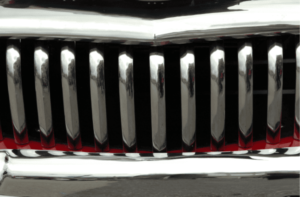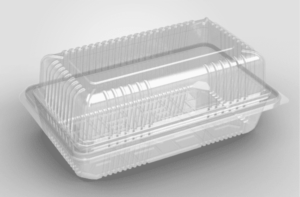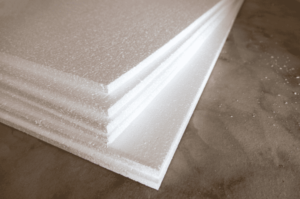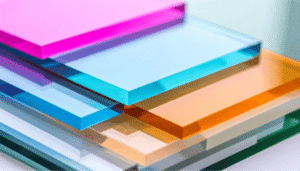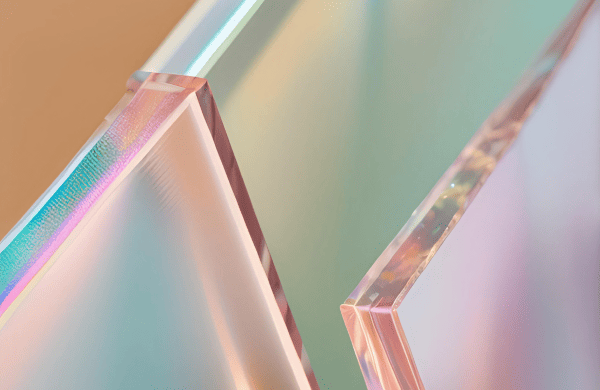
アクリル製品の静電気対策
帯電防止剤の選び方と活用方法
◆ アクリル加工現場における静電気の問題
アクリル(PMMA)は光学性・加工性に優れる一方、高い絶縁性と摩擦帯電性を持つため、加工・搬送・組立の各工程で静電気トラブルが頻発します。
代表的な現場課題は以下の通りです。
- 加工後の表面への粉塵付着
切削・研磨粉や環境中の微粒子が帯電により吸着し、外観不良の原因となる。 - 保護フィルム貼付時の異物混入
フィルム剥離時の帯電でほこりを引き寄せ、貼り込み後に混入物が発見される。 - 印刷・塗装工程での不良
帯電によるパーティクル付着で塗膜のピンホールや印刷不良が発生。 - 自動搬送ラインでのトラブル
静電気放電によるセンサー誤作動や電子部品への影響。
これらは歩留まり低下や再加工コスト増加を引き起こし、特に光学部品や意匠部品の生産では重大なロスとなります。
◆ なぜアクリルは静電気を帯びやすいのか?
アクリルは絶縁性の高い樹脂であり、電気を通しにくい特性を持ちます。摩擦や接触によって表面に電子が移動すると、その電荷が逃げずに表面に蓄積されます。これが静電気です。
主な原因は以下の通りです。
- 摩擦帯電
布や紙、他の樹脂と擦れることで電子が移動。 - 低湿度環境
湿度が低いと空気中の水分が少なく、電荷が放電しにくくなる。 - 絶縁性の高さ
アクリルは電気抵抗が高く、帯びた電荷が長時間残留。
◆ 従来の静電気対策の課題
静電気対策としては、アース設置、イオナイザー、帯電防止フィルムなどが一般的ですが、現場では以下の課題が残ります。
- 設備投資コストが高い(イオナイザーや除電ブロワー)
- 大物・非定形部品への対応が困難
- 既存製品や完成品には施工できない(添加型樹脂)
- 作業エリア限定でしか効果が得られない
そのため、柔軟かつ低コストで導入できる方法が求められています。
◆帯電防止剤の基本原理
帯電防止剤は、アクリル表面に導電性の薄い膜を形成し、表面抵抗を下げることで電荷を逃がします。種類は大きく分けて以下の2つです。
① 塗布型(表面処理)
- 使用方法:スプレーやワイピングで塗布。
- 特長:施工が簡単、完成品や加工途中のワーク表面に直接塗布が可能。
- デメリット:添加型と比較して、耐久性が落ちる。
② 添加型(練り込み)
- 使用方法:アクリル樹脂に帯電防止剤を混合して成形。
- 特長:耐久性が高く、長期にわたって効果が持続。
- デメリット:既存製品には適用できない、透明性や機械強度への影響の可能性あり。
🔍 まとめ
アクリル成形・加工現場では、静電気による異物付着が歩留まり・品質・工数に直結します。
塗布型帯電防止剤は、
- 設備投資不要
- 即効性あり
- 大物・変形品に対応可能
という現場メリットがあり、特に工程内での不良低減とコスト削減に有効です。
既存の静電気対策に加えて、「最後の一手」として導入することで、品質安定化に寄与します。