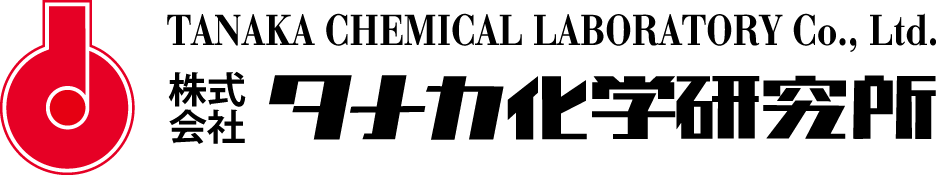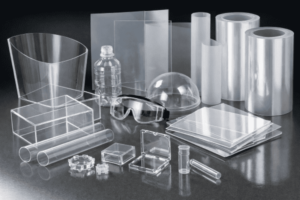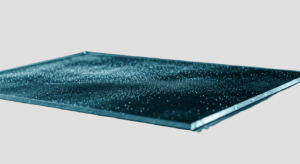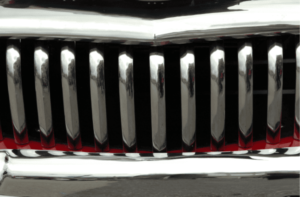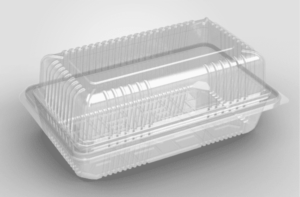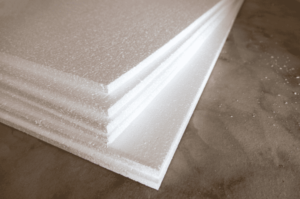静電気と湿度の関係
冬場に増えるトラブルと帯電防止の最新対策
◆はじめに
冬のオフィスや工場で「バチッ」とした不快な静電気を経験された方は多いでしょう。特に乾燥した季節には静電気が発生しやすくなり、日常生活だけでなく製造現場や精密機器を扱う業種にとって深刻な問題となります。本記事では 静電気と湿度の関係 を解説するとともに、静電気対策に欠かせない 帯電防止剤 の活用方法をご紹介します。
◆静電気が発生する仕組み
静電気は「物体の表面に電荷が溜まる現象」です。摩擦や接触・剥離などの動作で電子の移動が起こり、プラスとマイナスの電気のバランスが崩れることで発生します。
- プラスチック同士の摩擦
- 人が床を歩くときの靴底と床材との接触
- ライン作業でのフィルム・樹脂部品の取り扱い
これらは代表的な静電気発生要因であり、産業現場では 製品不良、粉じん付着、火災・爆発リスク に直結することもあります。
◆湿度と静電気の深い関係
静電気は 湿度が低いと発生しやすく、高いと抑制される という性質があります。
①湿度が低いとき
- 空気中の水分が少なく、絶縁状態が強くなる。
- 電荷が逃げ場を失い、物体の表面に帯電しやすい。
- 特に相対湿度30%以下で静電気トラブルが多発。
②湿度が高いとき
- 水分が導電路となり、電荷が拡散して逃げやすい。
- 帯電電位が下がり、放電現象が減少。
- 室内湿度40~60%程度が静電気抑制に有効。
このため冬場や乾燥地域では静電気事故のリスクが増し、帯電防止の工夫が欠かせません。
◆加湿だけで十分? ― 限界とリスク
湿度を上げることは静電気抑制に有効ですが、次のような問題もあります。
- 加湿によるカビ・結露のリスク
- 製品によっては湿気で品質劣化が発生
- 大型工場では加湿設備のランニングコストが増大
つまり「湿度管理だけ」では完全な静電気対策は難しく、現場環境に合わせた 帯電防止剤の導入 が求められます。
◆帯電防止剤でできること
帯電防止剤は、素材や表面に薄い導電性の層を形成し、電荷を拡散させて静電気を溜まりにくくします。
主な効果
- 静電気による ホコリ・粉じん付着の防止
- 樹脂やフィルム加工時の歩留まり改善
- 精密機器や電子部品の 静電破壊リスク低減
- 作業者の 安全性向上(感電防止・火災リスク低減)
特にプラスチック製品や塗装・成型工程では必須の対策といえます。
◆湿度管理+帯電防止剤の併用がベスト
静電気トラブルを根本的に抑えるには、以下の組み合わせが効果的です。
- 湿度40~60%を目安に加湿
- 帯電防止剤を樹脂や表面に処理
- 導電マットやアースを併用
この多層的なアプローチにより、安定した帯電防止効果が得られます。
◆帯電防止剤の選び方
現場や製品に適した帯電防止剤を選ぶことが重要です。
- 水系タイプ:安全性が高く、環境負荷を軽減。
- 溶剤系タイプ:速乾性に優れ、プラスチック塗装工程に最適。
- 樹脂混練タイプ:成型品全体に導電性を持たせたい場合に有効。
用途やコスト、求められる性能に応じて最適な製品を選択することがポイントです。
🔍まとめ
静電気と湿度は密接に関係しており、乾燥環境では静電気が発生しやすくなります。しかし湿度管理だけでは限界があり、確実な対策には 帯電防止剤の活用 が欠かせません。
弊社では、樹脂加工・塗装・フィルム製造など多様な現場で使用できる 帯電防止剤 をラインナップしています。