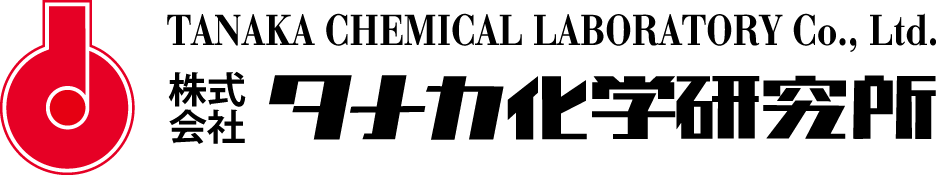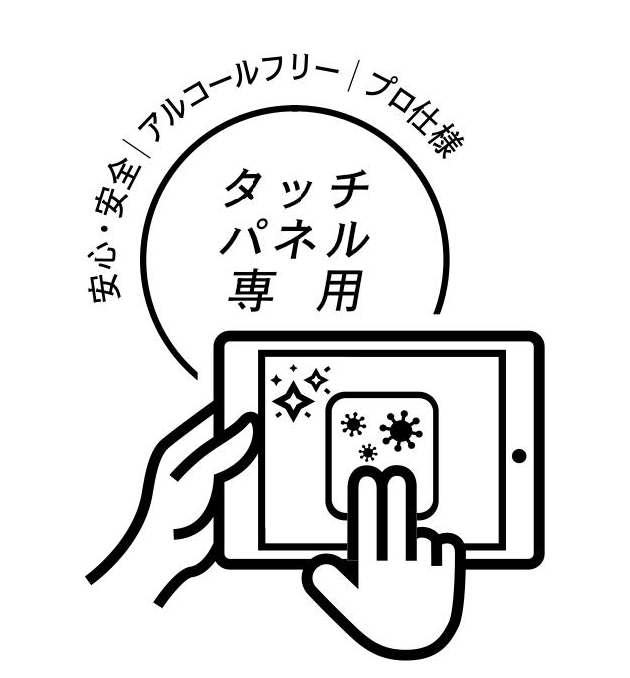OAクリーナーと液晶クリーナーの違いと使い分け
精密機器を正しく美しく保つための基本ガイド
オフィスや家庭で日常的に使われるパソコンや液晶ディスプレイ、タブレット端末、プリンターなどの精密機器。これらのデバイスを長く快適に使うためには、定期的なクリーニングが不可欠です。
そこで登場するのが、「OAクリーナー」や「液晶クリーナー」といった専用の清掃アイテム。しかし、いざ選ぼうとすると、「どっちを使えばいいの?」「同じじゃないの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、それぞれのクリーナーの用途の違い、使い分けのポイント、間違った使用のリスクまで詳しく解説します。最後まで読めば、オフィスや家庭で大切な機器を傷めることなく、清潔に保つ方法が分かります。
◆ OAクリーナーとは?
「OAクリーナー」とは、「Office Automation(OA)機器用クリーナー」のこと。主に以下のような電子機器の外装部やキーボード、プリンターの外面、ファクスなどの掃除に使われる製品です。
◎特徴
- 溶剤や界面活性剤を含むタイプが多く、油汚れや皮脂汚れに強い
- 速乾性があり、拭いた後にベタつきが残らない
- 一般的に静電気防止剤が添加されており、ほこりの再付着を防止
◎代表的な使用対象
- キーボードやマウス
- プリンター外装、電話機
- OAデスクや周辺機器の筐体
- プラスチック製品全般
◆ 液晶クリーナーとは?
「液晶クリーナー」は、液晶ディスプレイ(LCD)やタブレット、スマートフォンの画面などの繊細な表示面を掃除するための専用クリーナーです。
◎特徴
- アルコールや強い洗浄成分を含まない中性タイプが主流
- 画面に優しい成分設計で、コーティングを傷めにくい
- 拭き跡が残りにくい
◎代表的な使用対象
- パソコンやテレビの液晶画面
- スマートフォン、タブレットの画面
- デジタルサイネージや業務用タッチパネル
◆それぞれの違いを比較表で確認!
| 比較項目 | OAクリーナー | 液晶クリーナー |
|---|---|---|
| 主な用途 | 外装や筐体、キーボードなどの掃除 | 液晶画面やタッチパネルの掃除 |
| 洗浄力 | 油汚れに強い | 優しい洗浄力でコーティングを守る |
| 成分 | アルコール・界面活性剤含有タイプも多い | ノンアルコール・中性タイプが主流 |
| 静電気防止機能 | 含まれる場合が多い | 含まれる製品もある |
| 拭き跡・仕上がり | やや残ることがある | あと残りがしにくい |
| 素材への影響 | 強すぎると素材を痛める可能性あり | 素材に優しい処方設計 |
◆ 使い分けのポイント|こんなときはどっちを選ぶ?
● キーボードやマウスの汚れが気になるとき
→ OAクリーナーがおすすめ。皮脂やホコリをしっかり落とし、静電気防止効果で清潔が長持ちします。
● ノートパソコンの液晶が指紋でベタベタ
→ 液晶クリーナーを使用。OAクリーナーでは画面のコーティングを傷めたり、あと残りが出る可能性があります。
● オフィスの備品をまとめて清掃したい
→ OAクリーナーと液晶クリーナーを用途別に使い分けるのがベスト。特に多人数が使う共用PCや複合機は皮脂・菌汚れがつきやすく、しっかり除去できるOAクリーナーが便利です。
◆間違った使い方に注意!|よくある失敗例とそのリスク
●OAクリーナーで液晶画面を拭いてしまう
- 成分によっては画面のコーティングを傷めたり、あと残りすることがあります。
- 長期的には液晶に色ムラや劣化を引き起こす恐れも。
●液晶クリーナーでキーボードの奥を掃除
- 洗浄力が優しいため、頑固な油汚れは落としきれないことも。
- 雑菌が残ってしまう場合があります。
◆使用頻度とメンテナンスのコツ
- 週1回程度の清掃で機器の寿命が大きく変わる
- 汚れがひどいときは、1回で済ませようとせず数回に分けて掃除
- 清掃後は乾いたマイクロファイバークロスで仕上げ拭きすると仕上がりが格段に向上
◆おすすめのクリーナー選び方のポイント
- 使用対象を明確にして選ぶ(液晶か筐体か)
- 成分表示を確認し、アルコールや界面活性剤の有無をチェック
- 拭き取り用のクロスも重要。マイクロファイバー素材がベスト
🔍OAクリーナーと液晶クリーナーの使い分けが大切
OAクリーナーと液晶クリーナーは、どちらも精密機器の美観と衛生を保つうえで欠かせないアイテムですが、目的と使用対象が異なるため、正しく使い分けることが大切です。
- キーボードや外装には「OAクリーナー」
- ディスプレイやタッチパネルには「液晶クリーナー」
この基本さえ押さえておけば、あなたのデバイスはいつもピカピカ。さらに寿命も延び、仕事効率や衛生環境も向上します。
もし職場でのメンテナンスを効率化したいと感じているなら、業務用の高性能クリーナーの導入もぜひ検討してみてください。